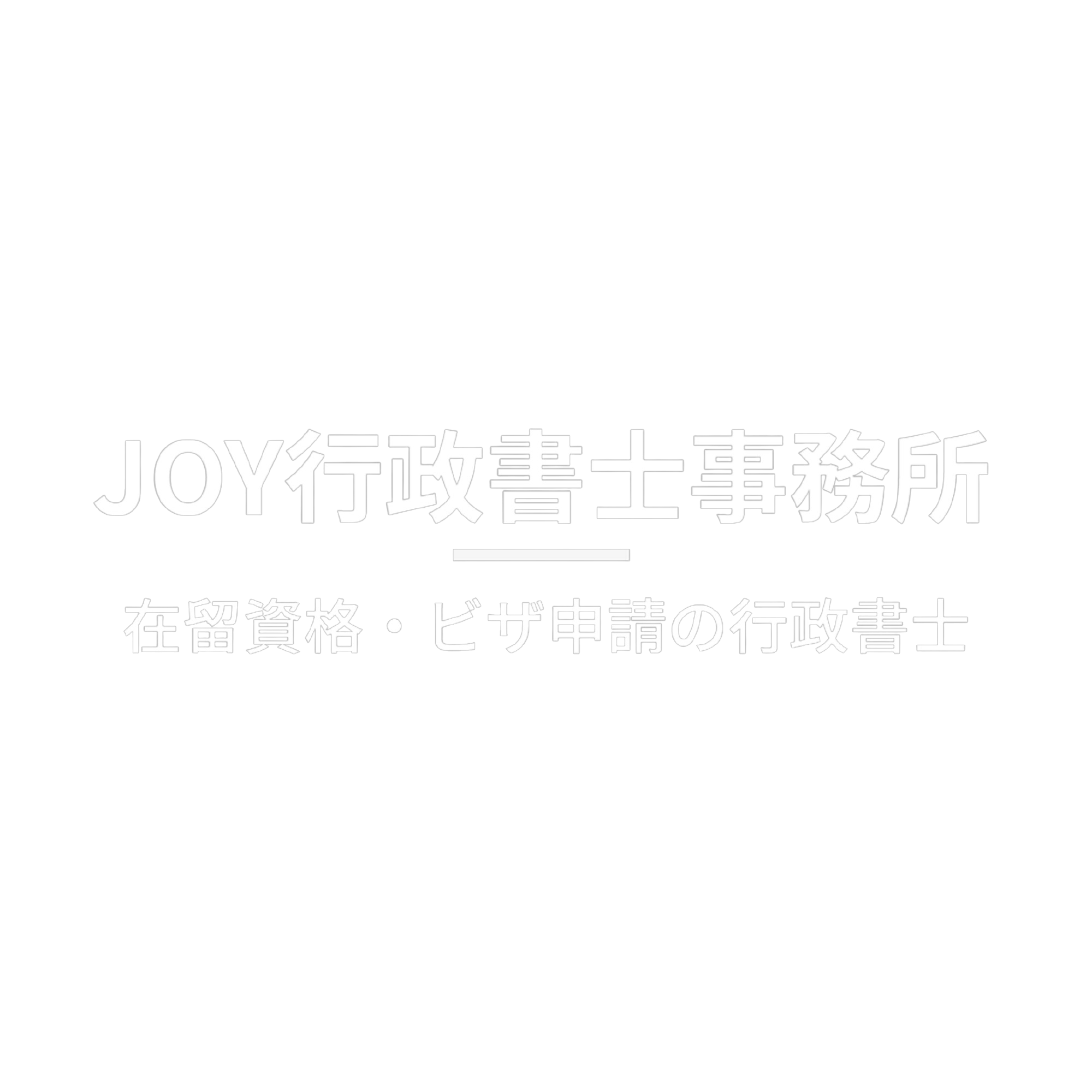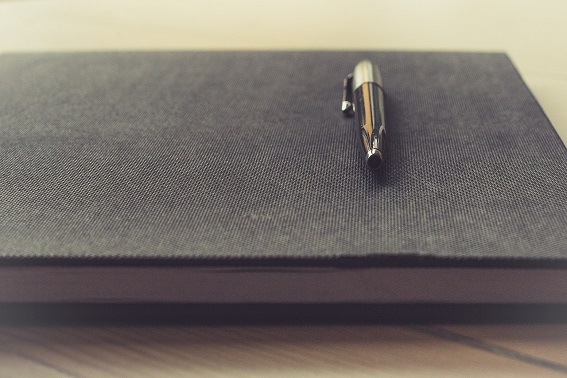在留資格「家族滞在」は配偶者と子どもしか認められていません。
「家族」なのに配偶者と子どもだけなの?と不思議に思ってしまいますが、日本語はあいまいな言葉とはよくいったものです。
在留資格・ビザを英語にして確認していくと、その在留資格・ビザのポイントがよくわかるかもしれません。
在留資格「家族滞在」と「教育」を英語にしてみましょう。
「家族滞在」を英語にすると?
在留資格「家族滞在」は英語では「Family」ではなく「Dependent」です。
「Family」と「Dependent」のちがいですが、いまはやりのChatGPTに確認をしてみましょう。
「Family」
意味::家族全体を指します。親、子供、配偶者、兄弟姉妹、祖父母などが含まれることがあります。
使い方: 家族の絆や関係を表すときに使われます。
「Dependent」
意味:経済的・生活的に誰かに依存している人を指します。通常、扶養家族(子供、専業主婦/主夫の配偶者、高齢の両親など)が該当します。
使い方: 税金や保険の文脈で、扶養されている人を指すときに使われます。
「Family」では配偶者(結婚相手)・子供以外にも親・兄弟姉妹・祖父母まで含まれてしまいます。
「Dependent」も同じ家族ですが、経済的・生活的に本体者に依存をしている扶養家族がくわしい日本語になります。
だから在留資格「家族滞在」の英語は「Family」ではなく「Dependent」のほうが正しいのです。
親・兄弟は「家族滞在」では呼び寄せることができませんし、配偶者や子どもであっても経済的・生活的に独立ができないため週28時間しかアルバイトができません。たくさん働くためには在留資格を変更しなければいけません。
高齢の親とはいえ、年金などで生活をしている親を「家族滞在」で呼び寄せることができないことも在留資格を英語にすることでわかります。
親を扶養することもありますが、基本的に親は独立した生活費で生活をしています。
「教育」を英語にすると?
専門学校の先生として働くとき、「教育」の在留資格の申請を考えますが、業務内容によっては「教育」ではなく「技術・人文知識・国際業務」の申請をします。
出入国在留管理局は「教育」の在留資格では語学教師をまず考えます。小学校などに派遣されるALT(外国語指導助手)です。
実は在留資格「教育」は英語で「Teacher」ではなく「Instructor」なのです。
「Teacher」と「Instructor」のちがいもChatGPTで確認をしましょう。
「Teacher」
意味:とくに学校で人々に知識やスキルを教える人
使い方:単に知識を伝えるだけでなく、生徒の成長や教育全般に関わる役割を担うことが多い
「Instructor」
意味:特定のスキルや専門知識を指導する人
使い方:一般的に短期間や特定の分野において指導を行う人を指す
「Instructor」と聞くとスキーのインストラクターをイメージしますが、スキーのインストラクターの在留資格は「特定活動」です。
ただ短期間・特定の分野の指導を行うのはスキーのインストラクターも語学教師も同じといえます。学校で教えているかどうか、のちがいです。
「Teacher」は担任の先生をイメージしますが、在留資格「教育」は「Instructor」です。
担任の先生だからこそ「Instructor」ではありません。学校で教えるからといって「教育」の在留資格にあてはまるわけではありません。
ほかの特定分野(自動車学校の整備士の教員など)であっても、語学教師でないときは出入国在留管理局に「教育=Instructor」で申請ができるか確認が必要です。
上でご説明したとおり、出入国在留管理局が考える特定の分野は語学教師だからです。
「教育」の申請が難しいときは「技術・人文知識・国際業務」の申請を検討します。
まとめ
英語で在留資格を確認してみました。
「家族滞在」でどうして親・兄弟を呼ぶことができないのか。
「家族滞在」は「Dependent」=扶養家族のための在留資格だからです。親・兄弟が無職で扶養をしているといっても、扶養義務を超えた扶養のため「家族滞在」の許可は取れません。
高齢親と日本で生活をするためには「特定活動」の申請をしなければいけません。
学校で教えるから、学校で働くからといって「教育」の許可は取れないかもしれません。
「教育」は「Instructor」として特定の分野を学校で教えるときに許可が取れます。
出入国在留管理局はその特定分野を語学教師と考えています。ほかの分野を教えるときは出入国在留管理局に確認が必要です。
お気をつけください。